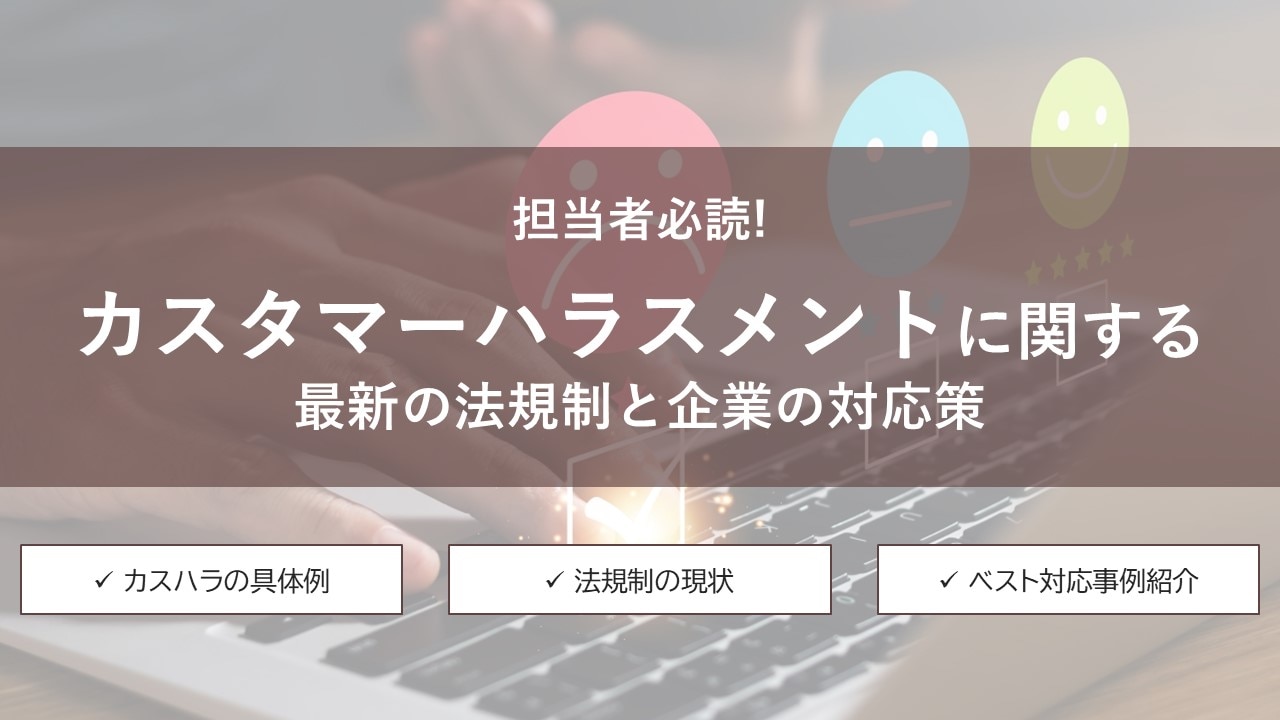
カスタマーハラスメントに関する最新の法規制と企業の対応策
※本記事は、掲載時点において公開されている情報に基づいておりますので予めご了承ください。
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)が大きな社会問題となっています。顧客から従業員に対する暴言や暴力、理不尽な要求などのハラスメント行為は、従業員の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるだけでなく、企業イメージの低下や業績への悪影響も招きかねません。
こうした中、企業にはカスハラへの適切な対応が強く求められるようになってきました。2020年には労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)防止措置が義務化されるなど、ハラスメントの法規制の強化も進んでいます。カスハラを放置することは、従業員の心身の健康を脅かすだけでなく、訴訟リスクにもつながりかねない重大な問題なのです。
本記事では、カスハラの定義や具体例、企業や従業員に与える影響、法規制の現状と課題、そして企業にとってカスハラ対策が重要な理由について解説します。さらに、社内規定の整備や従業員教育、相談窓口の設置など、効果的な対策の実践方法や、対策を進める上でのポイントについてもご紹介します。カスハラに対し企業に求められる対応とは何か、一緒に考えていきましょう。
カスタマーハラスメントの定義と問題点
まず初めに、カスハラの定義と問題点について解説していきます。
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは: 顧客や取引先などの外部の人から、従業員に対して行われる著しい迷惑行為や人格を否定するような言動 |
近年、サービス業を中心に顧客からの理不尽なクレームや暴言、暴力行為などが社会問題化しており、企業はカスハラ対策に乗り出す必要に迫られています。
カスハラは、
- 従業員の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させる
だけでなく、対応の仕方によっては
- 企業イメージの低下や業績への悪影響など、企業経営にも大きな打撃を与えかねない
深刻な問題です。
適切な対応を取らなければ、
従業員の離職率上昇やメンタルヘルスの悪化
従業員に対する安全配慮義務を尽くさなかったとする訴訟リスクの増大
など、様々な負の連鎖を引き起こしかねません。
こうしたカスハラに企業が組織として対応していくための出発点は、まず定義を明確にすること、そしてそれを社内で周知していくことです。
※参考※ |
カスタマーハラスメントの具体例
カスハラに当たりうる行為を分類すると、
verbal(言葉)
physical(身体)
sexual(セクシャル)の3つ
に分けられます。
たとえば、
こちらの3タイプに加えて、その他の迷惑行為等などがカスハラになります。 |
特に、接客業や営業職などの顧客と直接対面する機会が多い従業員ほど、カスハラの被害に遭いやすい傾向にあります。
顧客満足度を重視するあまり、正当なクレームとカスハラの区別を付けられずに、従業員に我慢を強いるような企業文化も問題を助長する要因の一つと言えるでしょう。
※ちなみに当社の整理では、行動類型だけではなく「就業環境を害する」という要件も満たしているかをカスハラの基準としているため、クレームとカスハラの区別があいまいになることはありません。
なお、カスハラは、従前より、法人間取引においても発生しています。
決して、対消費者に限った問題ではありません。
自社の取引先等に対して、自社の従業員がカスハラを行わないこと(加害者にならないこと)も重要です。
どのような行為がカスハラに当たりうるか、その行為類型を整理する場合は、法人間取引における取引先に対して行ってはいけない行為も例示しておくことが肝要です。
★ 担当者必見!★ → 【サービス紹介】カスハラ加害者にならないための取引先等に対するガイドライン 自社の従業員がカスハラの【加害者】にならないためにどんな準備をすればよいか、お困りではありませんか?
そんなガイドラインを提供しています!ぜひチェックしてみてください。 |
カスタマーハラスメントがもたらす企業への影響
カスハラを放置すれば、企業は様々な損失を被ることになります。
大きくは、4つのロスです。
時間的ロス | 長時間の対応を余儀なくされたり、繰り返しの対応をしたりすることで時間をロスすること |
金銭的ロス | 本来いただけるはずの費用をいただけないことなどで売上や利益の減少が起きること |
精神的ロス | 誹謗中傷や長時間の緊張状態を強いられるストレスで精神的負担が大きくなること |
人材ロス | ストレスや誹謗中傷を繰り返し受けることで対応を負担に感じ、それを原因としてモチベーションが低下し、退職につながってしまうこと |
これらの4つのロスが原因で人材確保に大きな影響を及ぼし、現場が回らなくなるなどの間接的な影響が出て、収益を低下させてしまいます。
そして、カスハラを看過したことで、安全配慮義務に関して従業員から訴訟を起こされ損害賠償請求を負うことや、それに伴う風評被害を被ることにもなりかねないのです。
カスタマーハラスメントが従業員に与える影響
カスハラの被害者となった従業員は、肉体的・精神的に大きなダメージを受けます。
顧客からの暴言や理不尽な要求にさらされ続けると、こんな事態につながります。
ストレスが蓄積し、うつ病などのメンタル不調を引き起こす
自分の対応の未熟さを責められ、自己肯定感が著しく低下してしまう
周囲からの支援が得られない状況では、一人で問題を抱え込むしかなく、離職せざるを得なくなる
経営者や管理職は、カスハラの実態を正しく認識し、従業員の心身の健康を守るためにも、適切な対策を講じる必要があるのです。
組織的な取り組みとして十分なカスハラ対策を行い、安心して働ける職場環境を実現することが求められています。
カスタマーハラスメントに関する法規制の現状
本章では、カスハラに関する現行法の規制状況とその課題について概観します。
現行法におけるカスタマーハラスメント対策の位置づけ
2025年4月現在、カスハラを直接規制する法律は存在しませんが、
労働契約法や労働安全衛生法などの労働関連法規において、労働者の安全と健康を確保する義務が事業主に課されている
カスハラによる精神的な不調が、労災認定の基準に加えられている
そのため、これらの法律に基づき、事業主はカスハラから従業員を守るための措置を講じる必要があります。
具体的には、
ハラスメント防止のための方針の明確化
相談窓口の設置
被害者への支援 などが求められます。
2020年6月の労働施策総合推進法の改正とその影響
2020年6月の労働施策総合推進法が改正されました。
これにより、職場におけるパワハラ防止措置が事業主の義務として明文化され、間接的にカスハラへの対策が強化されたと言えます。
また、改正法では、パワハラの定義が拡大されました。
取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)については、法律上の措置義務の対象とはしないが、指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載しています。
これにより、事業主はカスハラに対しても、パワハラ防止措置と同様の対応を取ることが求められています。
カスタマーハラスメント防止措置の義務化
現状では、カスハラ防止措置は法的な義務ではありませんが、将来的には義務化される可能性があります。
実際の事例としては以下のようなものがあります。
2024年10月4日、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(都条例)が可決・成立
→ 2025年4月1日より施行
→ これにより、都内の事業者はカスハラ防止に必要な体制整備に努めなければならなくなりました。2024年11月、北海道でも同条例が成立し、2025年4月1日より施行
他の府県でも同様の条例制定の動きがあり、厚生労働省が労働施策総合推進法改正案の検討に入っています。
厚生労働省が2022年1月に公表したカスハラ防止対策の指針では、事業主が取るべき措置として、以下の点が挙げられています。
|
これを受け、現在国会で審議されている労働施策総合推進法改正案では、カスハラ対策について、次のように規定されています。
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) |
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務) 第三十四条 2 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 |
従って、「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(義務規定:33条1項)」ことから、窓口設置、エスカレーション体制、対応要領の整備、組織的対応体制整備が必要になります。
また、「事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。(34条2項)」とされていることから、カスハラの加害者とならないための従業員への研修の実施等が要請されます。
企業におけるカスタマーハラスメント対策の重要性
ここでは、近年企業におけるカスハラ対策の重要性が高まっている理由と対策の必要性について詳しく見ていきましょう。
カスタマーハラスメント対策の必要性
これまで述べた通り、カスハラは、従業員の心身の健康を脅かすだけでなく、職場環境を悪化させ、生産性の低下にもつながります。
(東京都のカスハラ防止条例でも、基本理念の部分に「カスタマーハラスメントは、就業者の人格又は尊厳を侵害し、就業者の就業環境を害するとともに、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであり、社会全体でカスタマーハラスメントの防止を図る必要がある」と書かれています。)
さらに、適切な対応がなされない場合、企業イメージの悪化や法的責任を問われるリスクもあります。
したがって、企業はカスハラを防止し、発生した場合に適切に対処するための体制を整える必要があるのです。
適切な対応がもたらす企業イメージの向上
カスハラに適切に対応することは、企業イメージの向上にも寄与します。
顧客からの不当な要求や迷惑行為に毅然とした態度で臨み、従業員を守る姿勢を示すことで、社会的信頼を獲得することにもつながるのです。
また、ハラスメント対策に積極的に取り組む企業は、社会的責任を果たしているとみなされ、顧客だけでなく、従業員からの信頼も得られます。
優秀な人材の確保や定着率の向上にも好影響を与えるでしょう。
従業員の安全と健康を守る責任
企業には、従業員の安全と健康を守る責任があります。
カスハラは、従業員の心身に深刻なダメージを与える可能性があります。
長期的に暴言やストレスにさらされることで、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患を発症するリスクが高まります。
また、暴力行為によって身体的な怪我を負うこともあるでしょう。
こうした事態を未然に防ぐための対策としては、従業員教育の実施、相談窓口の設置、警備体制の強化などが挙げられます。
生産性の維持と向上
カスハラは、従業員の生産性にも大きな影響を与えます。
ハラスメントにさらされた従業員は、ストレスから集中力が低下し、業務のパフォーマンスが下がってしまう
ハラスメントによって心身の不調をきたした従業員は、休職や離職を余儀なくされるかもしれない
→ そうすると、人員不足や業務の滞留を招き、企業全体の生産性低下につながってしまいます。
したがって、カスハラ対策は、パワハラやセクハラへの対策と同様に、従業員の生産性を維持・向上させるためにも欠かせません。
従業員が安心して働ける環境を整えることが、企業の競争力強化にもつながるでしょう。
効果的なカスタマーハラスメント対策実践のための7つの柱
続いて、効果的なカスハラ対策の実践について当社で公表している「カスハラ対策7つの柱」に沿ってご紹介します。
1.自社のカスハラの被害・実態の把握 | まず行うべきことは、自社の「現場の実情」を把握することです。 対策を机上の空論とせず、生きた対策にするためには現状把握は欠かせません。自社にあわせた対策の出発点として、現場で対応する従業員に聞き取りを行うなどを行います。 |
2.カスハラ対応ポリシー(方針)の制定・明確化 | カスハラ対応ポリシーを作成します。そして社内外へ公表することで、企業姿勢を示します。 「従業員を守る」、「カスハラには企業組織として毅然な対応を取る」ということを明確にします。 |
3.カスハラへの対応要領の明確化 | 実際にカスハラが発生した際の対応方法や対応打ち切りの基準を明確にすることで、従業員が自信を持って対応に当たることができます。 対応要領と打ち切るためのロジックが重要です。 |
4.マニュアルの作成 | 方針や定義・行為類型・対応要領を明文化し、根拠作りをしてマニュアルに盛り込みます。そうすることで対応の標準化がしやすくなります。また、作成したマニュアルに則り教育・研修することで、生きた教材として使用できるものになります。なお、マニュアルは、一度作って終わりではなく、過不足や内容を修正しながら、ブラッシュアップしていくことが大切です。 → 【サンプルあり!】SPNの「カスタマーハラスメント対応マニュアル」サービスはこちら |
5.カスハラに関する研修の実施 | 従業員へ研修を実施します。まずはマニュアルの説明会を行い、対応方法についての研修を行います。その際、ロールプレイングを含んだ研修も実践的です。 |
6.カスハラ対応時のフォロー・サポート体制の整備 | 実際にカスハラを受ける従業員のフォロー・サポート体制と対応要領整備し、周知します。組織対応で対応者を孤立させない、安心感の醸成が結果的に従業員の精神的負担を軽減することに繋がります。 |
7.メンタルケア、従業員の保護対策の整備と運用徹底 | 上記までの体制を整えたとしても、精神的負担を強く感じてしまう従業員もいますので、早期にメンタルケアをする体制を整えます。そうすることで、精神的な障害を未然に防ぐことに繋がります。時には、法的対応が必要となる場合もあるため、法的措置を行うためのフロー図等を作成しておくことも必要です。 |
これからのカスタマーハラスメント対策のあり方
ここでは、今後のカスハラ対策のあり方について考察していきます。
法規制の動向と企業の対応の方向性
「カスタマーハラスメント防止措置の義務化」の章で取り上げた通り、カスハラに関する法規制は、現在のところ明確な基準が定められていませんが、今後の動向に注目が集まっています。
企業は、法規制の動向を踏まえつつ、自主的な対策を講じていく必要があるでしょう。
カスハラを防止するためには、まず企業側が問題の所在を正しく認識することが重要です。
繰り返しになりますが、顧客からの不当な要求や暴言、暴力などの行為を放置することは、従業員の心身の健康を害するだけでなく、企業の信頼やブランドイメージにも悪影響を及ぼします。
そのため、企業は社内規定の整備や従業員教育の充実といった対策を進めるべきです。
具体的には、
カスハラに関する社内ルールを明文化し、従業員に周知徹底を図ること
カスタマーサービス担当者向けの研修を実施し、適切な対応方法を身につけさせること
などが考えられます。
加えて、顧客とのコミュニケーションにおいては、一方的な対応ではなく、双方向の理解を深めるような働きかけが求められます。
例えば、サービスの利用規約を分かりやすく説明したり、顧客の意見や要望に真摯に耳を傾けたりすることで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
カスタマーハラスメント対策のベストプラクティス(事例紹介)
では、カスハラ対策の優れた事例にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、先進的な取り組みを行っている企業の事例を紹介します。
企業A(大手小売) | 全従業員を対象としたカスハラ防止研修を定期的に実施 実際の事例を基にしたロールプレイングを取り入れ、具体的な対応方法を学ぶ機会を設けています。また、カスタマーサービス担当者向けには、より専門的な知識やスキルを習得するための上級者研修も用意されています。 |
企業B | 顧客からのクレームや要望を一元管理するシステムを導入 迅速かつ適切な対応を可能にしています。このシステムでは、顧客の声を分析し、サービスの改善につなげる仕組みも整えられています。さらに、カスハラ対応指針をHPなど対外的にも明示し、悪質な顧客に対しては、法的措置を含めた毅然とした対応を取ることで、従業員を守る姿勢を明確にしています。 |
これらの事例に共通しているのは、トップダウンでカスハラ対策に取り組む姿勢と、現場の声を吸い上げる仕組みづくりです。
経営層が率先して問題に向き合い、従業員の安全と尊厳を守る方針を打ち出すことが、対策を進める上で欠かせません。
併せて、日々顧客と接する従業員の意見を反映させ、実効性のある対策を講じていくことが重要と言えるでしょう。
持続可能な企業経営におけるカスタマーハラスメント対策の位置づけ
最後に、持続可能な企業経営におけるカスハラ対策の位置づけについて考えてみましょう。
カスハラ対策は、単なるリスク管理の一環ではなく、企業の社会的責任を果たす上で欠かせない取り組みと言えます。
近年、企業に対しては、財務面での健全性だけでなく、環境や人権への配慮、ステークホルダーとの良好な関係構築など、多面的な要素を踏まえた経営が求められるようになってきました。
こうした中で、従業員の尊厳を守り、安全で働きやすい職場環境を整備することは、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
カスハラ対策は、顧客満足度の向上や企業イメージの向上といった直接的なメリットをもたらすだけでなく、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高める効果も期待できます。
従業員が安心して働ける環境が整っていれば、サービスの質の向上にもつながります。
また、社会からの信頼や支持を得ることは、企業の長期的な発展に欠かせません。
カスハラを放置することは、企業の社会的評価を下げるリスクがあることはすでにお話したとおりですが、反対に、真摯な対策を講じる姿勢を示すことで、ステークホルダーからの理解と共感を得ることができるでしょう。
以上のように、カスハラ対策は、持続可能な企業経営を実現する上で、重要な要素の一つと位置付けられます。
企業は、この問題に正面から向き合い、自社の事業特性に合わせた実効性のある対策を確立していくことが求められています。
まとめ
カスハラは、企業にとって看過できない重大な問題です。
従業員の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させるだけでなく、企業イメージの低下や業績への悪影響も招きかねません。
2020年の労働施策総合推進法の改正により、カスハラ対策は法的にも強化されつつあり、東京都をはじめとした都道府県単位での防止条例の制定も進んでいます。
企業には、明確な方針の下、社内規定の整備や従業員教育、相談体制の構築など、多角的な対策が求められています。
加えて、カスハラ事例の収集・分析を通じて、継続的な改善を図ることが肝要です。
こうした取り組みは、従業員の心身の健康を守り、生産性の向上や企業価値の向上につながります。
カスハラ対策は、もはや企業の社会的責任と言えるでしょう。
ハラスメントのない職場づくりは、持続可能な企業経営の礎となります。
法規制の動向を注視しつつ、従業員の声に耳を傾け、実効性のある対策を確立していくことが、今の企業に求められているのです。
エス・ピー・ネットワークでは、豊富な実績とノウハウを活かし、企業のカスハラ対策をサポートしています。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。







